【実践紹介⓪】 「モチモチの木」で登場人物の性格を想像する 〜教材分析と単元構成〜
公開日: 2024年10月18日金曜日 「モチモチの木」(光村図書・東京書籍3年)
本校3年目の木下 忠志と申します。今年度は3年3組を担任しています。
今回は「モチモチの木」を教材にした実践を紹介させていただきます。
⑴ 本作品の特徴 〜登場人物の性格を想像するということ〜
皆さんは、物語を読むときに人物の性格を想像しながら読んでいますか?
私は「登場人物の性格」とは、物語が展開する中で、登場人物の行動や心情に共感したり、反発したりしながら読み進めるうちに、登場人物への愛着を抱き、物語を読み終わった後に、読後感のように味わうことが多いのではないかと考えています。
本学習材「モチモチの木」には、「おくびょう」「勇気がある」「優しい」などの性格を表す叙述が多く描かれています。そのため、豆太の性格を捉える際に、「臆病」なのか「勇気があるのか」。「最初と最後で豆太は変わったのか」を扱う実践は多いのではないでしょうか。
しかし、山中(2015)は、「豆太はもともと勇気のある子であるとか、おくびょうとかレッテルをはれるような存在ではありません。普通の素朴な、あるがままの豆太です。普通の子どもと少しも変わりはないのです。」と述べています。
つまり、「豆太」という人物は一言で性格を言い表すことができず、場面や状況によって様々な一面を見せる人間味あふれた登場人物であると言えるでしょう。そして、本教材は物語終末の一文に「これまでと変わらない豆太」を描くことで、読者に「豆太とは」を改めて想像させ、もう一度物語を読み返したくなる工夫がなされています。
豆太の性格を捉える時。登場人物の境遇や状況、場面の様子、他の登場人物が豆太をどう捉えているのかを結び付けながら多面的に捉えることで、人間味溢れた登場人物のとして物語をより読み味わうことができると思います。
⑵ 本学級の子どもたち
本学級の子どもたちは、これまでにも物語作品を学習する中で登場人物の性格について「おっとりしている」「好奇心旺盛」などの言葉で表現していました。
これは、登場人物の多くが物語を通して一貫した性格で描かれているため、子どもたちにとっても捉えやすいからであると考えます。
しかし、上述したように、本来性格とは一面的に語ることのできない様々な面をもっているものです。そこで、そのような子どもたちに本教材「モチモチの木」に出合わせることで、登場人物を多面的に捉えながら物語を読み味わい、文学のおもしろさを実感してほしいという願いをもち、単元を構想しました。
⑶ 言語活動『みんなで語る豆太語り』について
⑴でも述べたように本教材は、五つの場面によって構成されています。教科書ではそれぞれの場面に題名が付けられているため、一読すると物語の展開をおよそつかむことができるます。物語は「語り手」によって語られ、語り手から見た豆太が語られていたり、じさまや豆太に寄り添って語られていたりします。
そこで、本実践では『みんなで語る豆太語り』という言語活動を核とした単元を構想します。場面の移り変わりを結び付けながら、登場人物の境遇や状況を捉え、行動や会話、他の登場人物が語る豆太の性格を表す言葉に着目しながら、登場人物の性格を具体的に想像する力の育成をねらいます。
本教材は「語り手」の視点から物語が始まり、じさまや豆太に寄り添いながら物語が語られていきます。そして、最後の一文では、山場とは異なる変わらなぬ豆太の姿が語られるため、子どもたちは疑問をもち、それぞれの思う「豆太の性格」を呟き始めることが予想されます。
しかし、一読しただけでは豆太の性格を具体的に想像することは難しく、「もっと読みたい」という思いが出ることが予想されます。
そこで、「語り手」「じさま」「豆太」の人物の視点に立ちながら、それぞれが語る豆太の性格を手がかりにし、各場面の行動や会話を劇化したり、場面の移り変わりや登場人物の境遇や状況を結び付けたりしながら、「豆太の性格」を多面的に想像していくことができるようにしていきます。
本実践の主張は以下の2点です。
○「語り」の構造を生かし、「語り手」「じさま」「豆太」の立場になってみること(同化)と、それを見る(異化)ことで豆太の性格を多面的に捉えることができるようにする。
○ 言語活動『豆太語り』に取り組み、読者(異化)として豆太の性格を語ることで、場面の状況や人物の行動、他の人物の言葉などを結び付け、性格を具体的に想像することができるようにする。また、子どもが言語化した表現は「語り手帳」に記述し、「豆太語り」に生かせるようにする。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
次回のブログからは、実践の様子を紹介していきたいと思います。
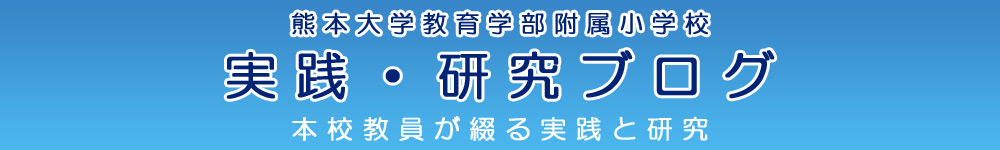
このコメントは投稿者によって削除されました。
返信削除