「大造じいさんとガン」(5年)教材研究 〜「なぜ大造は銃を下ろしたのか」の先に〜(学習指導案・実践編・授業記録あり)
公開日: 2021年2月11日木曜日 「大造じいさんとガン」(光村図書/東京書籍5年) 教材研究
黒の背景に白い文字。
おなじみ,NHKのドキュメンタリー番組「プロフェッショナル-仕事の流儀-」の象徴的な演出です。
今回,「大造じいさんとガン」を学習材とした実践を構想するにあたり,私はこの「プロフェッショナル」を言語活動の素材として考えました。
ここでは,「大造じいさんとガン」の教材分析を基に,なぜ私がこの「プロフェッショナル」を言語活動の素材として選んだのかについてお話ししたいと思います。
※本実践は、令和2年度のものです。
令和5年度実践は、こちらからご覧いただけます。
併せてお読みいただければ幸いです。
<ダウンロード資料はこちらから>
・実践編
・授業記録
「なぜ銃を下ろしたのか」という「行動の理由」のみを読むのでは不十分
「大造じいさんとガン」の授業では,クライマックス場面が取り上げられ「なぜ大造じいさんは銃を下ろしたのか」「大造じいさんは何に心を打たれたのか」など,「行動の理由」や「心情の変化」についての問いが扱われることが多く見られます。
しかし「行動の理由」は低学年,「心情の変化」は中学年の指導事項です。
高学年ではそれらを基に「人物像を具体的に想像する力」をつけていくことが求められます。
つまり,「残雪に対する見方が変わったんだ」「残雪の堂々とした姿に心を打たれたから銃を下ろしたんだ」という読みでは,高学年としては不十分だということです。
私は,今回の実践で「人物像を具体的に想像する力」を重点指導事項に設定しようと考えました。
「ここで撃たなかった大造じいさんは,こんなものの見方をしているな」
「でもそもそも大造じいさんってこんな性格だったよな」
「大造じいさんのいう『ひきょうなやり方』『堂々と』ってこんな考え方なんだ」
このような思考過程を辿りながら,人物像を物語全体を通して総合的に判断していくことができるようにしたい。
そんな願いをもち『プロフェッショナル-大造の流儀-』を創るという言語活動を設定しました。
以下,「大造じいさんとガン」を「指導事項」と照らし合わせながら分析しながら,その具体について述べてみたいと思います。
「学習材の特徴」と「身に付ける力」
本学習材「大造じいさんとガン」は,大きく「前書き」と「本文」に分けられます。
前書きからは,作者である「わたし」が,大造じいさんの人柄や「愉快なかりの話」の魅力に惹きつけられ,その中の一つとして語られた「三十五,六年も前」の「ガンがりの話」を土台に,この「大造じいさんとガン」という物語を作ったことが読めます。
本文は,「1」〜「4」のエピソードに区切られており,典型的な起承転結の構成となっています。
初め,大造じいさんの残雪に対する見方は「いまいましい」「たかが鳥」だったが,「1」のウナギつりばり作戦,「2」のタニシばらまき作戦を経て徐々に変化していきます。
さらに「3」のおとり作戦の決行中,突如現れたハヤブサに立ち向かい,傷を負ってなお毅然とした態度で自分の前に立つ残雪の姿を目の当たりにし,「ただの鳥に対しているような気がしない」とその見方が大きく揺り動かされます。
そして,「4」では,残雪に対して「ガンの英雄」「えらぶつ」「おれたち」「また,堂々と戦おうじゃないか」と呼びかけているように,大造じいさんが,残雪を自分のよきライバルと認め,清々しい気持ちで去りゆく姿を見送っていることがうかがえます。
つまり,この物語の特徴として,山場での出来事をきっかけに,中心人物のものの見方や考え方が大きく変化が挙げられます。
その特徴を生かして教材化する上で,「中心人物のものの見方や考え方」を生かせば「人物像」を,「山場での変化」を生かせば「物語の全体像」を重点指導事項とした学習の展開が考えられるでしょう。
また,豊かな情景描写や色彩語など,表現の効果を考えていくという展開も考えられます。
教科書による重点指導事項,言語活動の違い
本作品は,各教科書において,次のような単元名・学習のポイント・言語活動で扱われています。
どの教科書でも,文学的文章における精査・解釈の指導事項「エ 人物像や物語などの全体像を具体的に想像したり,表現の効果を考えたりすること」に重点を置いた単元構成となっています。
ただし,「たいせつ」「言葉の力」など,教科書で子ども向けに示された学習のポイントに着目すると,各社が精査・解釈の指導事項の中でもさらに重きを置いている部分が見えてきます。
また,それに合わせて,各社で異なる言語活動が設定されています。
例えば,光村図書と東京書籍で設定されている「朗読」は,どう読むかを考えることで優れた表現に着目させる意図をもった言語活動だと考えられるでしょう。
ただ,音声表現のため評価(自己評価・相互評価を含めて)が難しいかもしれません。
また,教育出版や学校図書のような感想交流では,「よりよい感想を書き上げる」という目的意識はもちづらいと考えられます。
『プロフェッショナル-大造の流儀-』では
→上記の会は終了しています
ぜひそちらの記事もご覧ください。
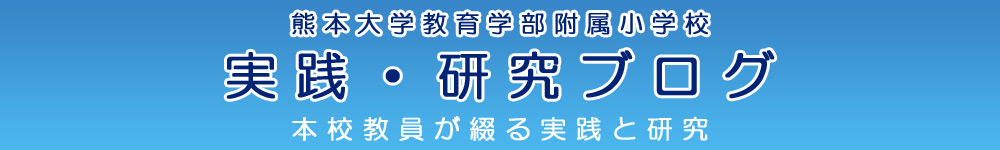


0 件のコメント :
コメントを投稿