【大造じいさんとガン】0次段階の工夫① 〜「のりしろの力」を振り返る〜
公開日: 2024年2月4日日曜日 「大造じいさんとガン」(光村図書/東京書籍5年)
単元びらき前に「0次段階の工夫*」として二つのことに取り組みました。
その二つとは、
・「のりしろの力」を振り返る
・「前書き」を活用した「大造じいさんとガン」への誘い
です。
今回は、一つ目の「のりしろの力」についてご紹介します。
*「0次段階の工夫」は、「国語科学習指導課程づくりーどう発想を転換するか」(大熊徹/2012/明治図書)を参考にしています。
その二つとは、
・「のりしろの力」を振り返る
・「前書き」を活用した「大造じいさんとガン」への誘い
です。
今回は、一つ目の「のりしろの力」についてご紹介します。
*「0次段階の工夫」は、「国語科学習指導課程づくりーどう発想を転換するか」(大熊徹/2012/明治図書)を参考にしています。
教科書には書いていないけれど、学びをつなぐ大切な力
「のりしろの力」という言葉は、以前佐賀大学の達富洋二先生に教えていただきました。
のりしろとは紙と紙を貼り合わせる(つなぐ)時に糊をつける部分です。学びと学びをつなぐにものりしろの力が必要です。しっかり考える力も、聞きながら書く力も、自分に必要な情報だけ取り出してノートに写す力も、短い時間で描き切る力も、《私の問い》を立てる力も、本を選ぶ力も、付箋紙を貼る力も、プリントを表向きにして揃えておる力も、辞書で調べるときは指をはさむ力もみんなみんなのりしろの力です。(「ここからはじまる国語教室」(達富洋二/2023/ひつじ書房)より引用)
学級ではこんな言葉で共有しました。
「教科書には書いていないけれど、学びをつなぐ大切な力」
その上で、前単元の学習をもとに、「どんなのりしろの力がついてきたか」を子どもたち自身で振り返る場を設けました。
子どもたちが見いだした「のりしろの力」
今回は小黒板を子どもたちに開放し、自分が選んだテーマでそれぞれ話し合いを進めました。
<みんなでの話し合い>チーム

<それぞれタイム(少人数)>チーム

<それぞれタイム(個人)>チーム
・今日はのりしろの力について考えました。私は、のりしろの力は日常生活でもいっぱい授業とかで使われていることにびっくりしました。のりしろの力は自分の意見と相手の意見をつなげて考えたりする力があるからすごいと思いました。
・僕は、個人だと「自分の考えを見直して考える力」「意見を書いてみる力」「考えをまとめてわかりやすくする力」、
少人数で話し合うだと「問いが同じ人と一緒に考える力」「自分の意見を相手に伝える力」「わからないことを話し合う力」、
大人数で話し合うだと「自分の考えたことを言葉に表す」ができているのではないかと思いました。「大造じいさんとガン」では、大人数で話し合うとき、自主的に交流するということをしたいです。
・私はじっくり読んで自分なりに解釈する力やみんなの話を聞くことで自分の問いやわからないこと(自身がないこと)を解決する力がついたかなと思いました。じっくり読んだ上で全体のつながり、流れを理解しようとすることができました。また、みんなと話すことで問いを立てて考えることができました。
きっと、学びが<自覚的>になる!
これまで、授業の中で暗黙知だった力を言語化・共有化したことで、これからの学びの質が変わるのではないかと思います。上で挙げた国語日記を見てもわかるように、子ども自身の意識も変わったでしょうし、私自身も「今日はどの<のりしろの力>が使えそう?/どの力を使った?」のようなシンプルな働きかけができるようになります。
これから、一人ひとりがどんな学びのプロセスを歩んでいくのか、とても楽しみになりました!
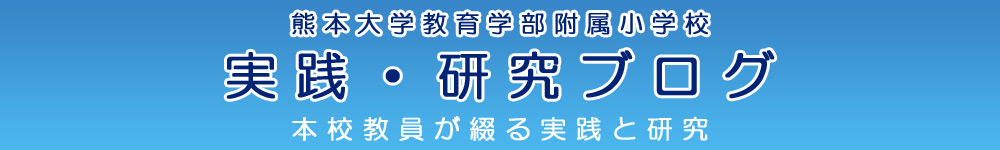

0 件のコメント :
コメントを投稿