たぬきの糸車 0時間目 ~教材分析・言語活動編~
公開日: 2025年10月14日火曜日
本校2年目の廣田です。
今年度は、1年生を担任しております。
素直でかわいい1年生の子どもたちと毎日楽しく過ごしています。
今回は光村図書「たぬきの糸車」の実践を紹介させていただきます。
【教材の特徴】
「たぬきの糸車」は岸なみさんによって書かれた作品です。1977年から教科書に掲載されており、長い間子どもたちに親しまれてきました。
あらすじは以下の通りです。
ある山奥に木こりの夫婦が住んでいました。きこりの夫婦の家には毎晩のようにたぬきがいたずらをしにきます。そこできこりはわなをしかけました。
ある月のきれいな晩のこと、おかみさんが糸車を回していると、やぶれ障子の穴からたぬきがのぞき、糸車を回すまねをしていました。おかみさんはそのたぬきをかわいく思いました。
けれどある晩、たぬきがわなにかかってしまいます。おかみさんは、かわいそうに思って逃がしてあげました
冬がくると木こりの夫婦は村におりていきました。春になって家に帰ると糸車のそばには山のように糸の束があります。そして、おかみさんは糸車を回すたぬきに気がつきました。
おかみさんがのぞいているのに気がついたたぬきは嬉しくてたまらないというように、ぴょんぴょこおどりながら帰っていきました。
糸車を通したおかみさんとたぬきの温かい関りが描かれている作品です。子どもたちは、たぬきを逃がしてあげたおかみさんの優しさや一生懸命に糸車を回す真似をするたぬきのかわいらしさなどにこの物語の魅力を感じるでしょう。この物語りの特徴をいくつか紹介します。
・三人称限定視点で書かれている物語で、中心人物であるおかみさんに寄り添いながら語られています。そのため、子どもたちはおかみさんの視点からたぬきのかわいらしさなどを感じることになります。逆にたぬきに目が行きがちな作品ではありますが、たぬきの心情などは書かれておりません。
・「くるりくるり」「ぴょんぴょこ」「キーカラカラ」などの声喩が多用されています。声喩が多用されていることによって、たぬきやかわいらしさや愛らしさがより強調されています。
・この物語は「伊豆の民話」が基になっており、岸なみさんによって教科書教材に書き変えられる際に、かなりの省略が施されています。その結果として、物語の空所が多く想像の余白が残されている作品です。例えば、民話ではたぬきの行動の理由(なぜたぬきはいたずらをしに来るのかなど)も書かれていましたが、教科書教材では書かれていません。また、おかみさんに目を向けても「たぬきのことをどんな思いで見ていたのか」などは語られていません。たぬきやおかみさんの行動の理由を想像することができる物語です。
こうした教材の特徴から、「たぬきの糸車」は、おかみさんの言動やたぬきの行動に着目し、その理由を考えることでより面白さを味わえる作品だと思います。
【言語活動について】
子どもたちはこれまで「はなのみち」「おおきなかぶ」「おむすびころりん」の単元の中で、劇遊びやインタビューなどの学習に取り組んできました。その学習では、劇遊びをする登場人物の表情や動きを叙述から具体的に想像したり、「おおきなかぶ」でのかぶの大きさや「はなのみち」でのくまさんとりすさんの家の距離などを具体的に想像し場面の様子を考えたりしてきました。
しかし、子どもたちの即興的な表現を取り上げて課題にしていたのは教師であり、子どもたち自身が登場人物の言動などに問いをもち、立ち止まって考えている姿は少なかったです。
しかし、前述したようにたぬきの糸車の面白さの一つは、たぬきやおかみさんの行動の理由を考えることにあると思っています。そこで、本実践では、「子どもたち自らが登場人物の言動に立ち止まり、立ち止まった言動の理由を考えることを通して、物語をより味わってほしい」という願いを込めて単元を構想します。
そのための手段として、本実践では「実習生にたぬきの糸車の素敵なところやいいところが伝わる手紙を書こう」という活動と「ホットシーティング」という活動を組み合わせた言語活動を設定します。
子どもたちがどのように登場人物の言動に立ち止まり、行動の理由を考えていきなながら物語を味わっていったのかを次のブログから紹介していきたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
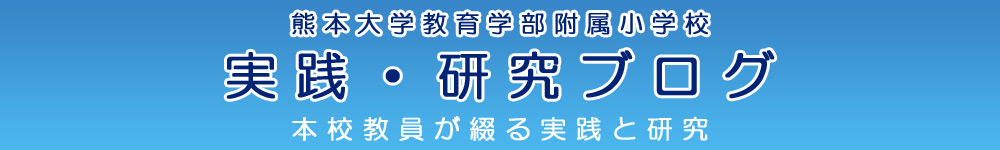
0 件のコメント :
コメントを投稿