たぬきの糸車 1時間目 ~なんでおかみさんはたぬきを逃がしたの?~
公開日: 2025年10月14日火曜日
たぬきの糸車1時間目です。
本時では、初めてたぬきの糸車と出合い、物語の大体を捉えていきます。そして、実習生にたぬきの糸車のすてきなところやいいところを伝える1通目の手紙を書いていきます。
本時の実際にうつるまえに、本学級での日常の取り組みを紹介します。本学級では日常的に読み聞かせを実施しています。この読み聞かせは、先生が読む本を子どもたちが黙って聞くようなものではなく、気になったことや感じたことがあれば自由に呟くことを許容しています。また、子どもたちの気になったことをきっかけに少し話し合いの時間をとることもあります。読み聞かせの中で「きっと次はこうなるよ。だって・・・」のように先を予想する発言が出てきたり、「え~。なんでそうするの?僕だったら・・・」のように自分と重ねた発言が出てきたりします。そうした発言を価値づけながら、読み方の種をどんどん蒔いています。
たぬきの糸車に入る少し前から、この読み聞かせの時間に昔話や民話を読み聞かせることを多くしていきました。昔話や民話に親しみをもってたぬきの糸車に出合ってほしいと思ったからです。
そして、その昔話や民話の読み聞かせの流れでたぬきの糸車にも出合いました。
【学習活動① 「たぬきの糸車」の題名読みをする】
本時はたぬきの糸車と初めて出合う一時間でもあったので、題名読みから想像を広げていました。まず、こくばんに「たぬき」だけを書き、「たぬき」に対するイメージを話し合っていきました。
T:たぬきってきいてどんなイメージが浮かびますか?
ここみ:くまみたいで、ぽんぽこりん
まさみ:ちゃいろのイメージ
CC:おうどいろのイメージもある
CC:目の周りは黒い
ゆうき:おなかをぽんぽこたたいてるイメージ
T:おなかをたたくってどういうこと?ちょっとやってみてよ
ゆうき:(おなかをぽんぽこたたく真似をする)
CC:そうそう、かわいい。
CC:うん、たしかに、かわいいイメージ
子どもたちは、たぬきの色や動きなどの様子からかわいいというイメージをもっているようでした。ここで、ちがった視点から考えられるようにするために、「お話に出てくるたぬきはどんなイメージか」を尋ねてみました。
T:お話の中にでてくるたぬきって聞いたらどんなイメージがする?
ゆかり:ん~、いたずら?
CC:あ~、ぶんぶくちゃがま!
CC:かちかちやまも!!
ここみ:前たぬきの絵本(かちかち山)見たときにちょっと悪そう。
CC:そうそう、だます感じ
子どもたちにとってお話の中に出てくるたぬきは少し悪いイメージがあるようでした。そこで、「自分にとってたぬきはかわいいイメージなのか。それとも悪いイメージか」を尋ねると、かわいいが13人、悪いが17人、分からないが6人となりました。この自分の中のたぬきのイメージによってたぬきの糸車を読むときの感じ方が変わってくると思います。たぬきに対して誰がどんなイメージをもっているのかを知っておくことで、今後の展開にも生かされてきます。
次に「の糸車」を板書しました。すると「糸車って何?」という呟きがあったので動画で糸車を確認し、「糸を作る道具であること」を確認していきました。その後、「どんなお話だと思う?」と尋ねると以下のような予想が出てきました。
・たぬきが糸車を回すお話
・たぬきが糸車にばけていたずらするお話
・たぬきが糸車にいたずらするお話
「どんなお話なのだろう。」という期待が高まったうえで物語の読み聞かせに入りました。
【学習活動② たぬきの糸車の読み聞かせを聞き、すてきなところやいいところを見つける】
前述したように、読み聞かせの時間の流れで
「たぬきの糸車」に出合うので、子どもたち
はどんどん呟きながらお話を聞きます。私は
その子どもたちの発言を広げたり、問い返し
たり、板書に残したりしながら進めていきま
す。その活動の中で、物語の大体の内容を整
理していきました。
どんなやりとりがあったか、抜粋して紹介します。
(冒頭の設定の場面)
T:やまおくのいっけんやなので、毎晩のようにたぬきがやってきていたずらをしました。
やまと:やっぱりね。やっぱ悪いことしにきた。
CC:やっぱりいたずらしに来るんだ。
T:みんなはこのいたずらをやっぱりって思ってるんだね。
そうた:そうそう。そしてわなをしかけられると思う。
しんた:わなしかけられそう!かちかち山といっしょで。
CC:確かにわな仕掛けられそう!
T:じゃあ続き読むね。そこできこりはわなをしかけました。
CC:あ~、やっぱり。
T:みんなの予想どおり、わなを仕掛けたね。このわなって誰が仕掛けたんだっけ?
CC:きこり。きこりのふうふ。
T:ふうふってみんなわかる?
CC:かぞくのこと。きこりとそのおくさん。
T:そうだね。じゃあ、このお話には、きこりとおかみさんとたぬきが出てくるよ。
いたずらするたぬきにわなをしかけたんだね。
このようにして子どもたちの発言をきっかけにしながら、「たぬきがいたずらをしにきていること」「きこりがわなをしかけたこと」などの出来事や登場人物をおさえていきました。
(おかみさんがわなからたぬきを逃がす場面)
T:「かわいそうに、わなになんかかかるんじゃないよ。たぬきじるにされてしまうで。」おかみさんはそういって、たぬきを逃がしてあげました。
CC:やさしい。
CC:え~、なんで。
りりな:いたずらだし、悪いやつなのになんで逃がしてあげたの?
たろう:おかみさんには悪いことしてないんじゃないの?
たつみ:小さくてかわいいからじゃないの?
T:少し近くの人と話してみようか。
しょう:逃がすなら、最初からわななんか仕掛けなきゃよかったのに。
CC:確かに。せっかく捕まえたのにね。
この場面では、子どもたちは「なぜおかみさんがたぬきを逃がしたのか」に疑問をもっているようでした。しょうさんの発言からも分かるように、子どもたちは、この逃がすという行為はわなを仕掛けた最初の行為からすると矛盾があるように感じています。この矛盾の裏にある行動の理由を考えていくと面白そうです。
(ぴょんぴょこおどりながらたぬきが帰っていく場面)
T:うれしくてたまらないというように、ぴょんぴょこ踊りながら帰っていきましたとさ。
かれん:たぬき、かわいい。よかったね。
T:なにがかわいかったの?
かれん:最初のたぬきはいたずらっこだったのに、最後のたぬきは悪いことしてなかった。
CC:そうそう、悪くなくなってたね。
T:そうなんだね。他にかわいいなって思った人いる?
しんた:最後にたぬきがぴょんぴょこ踊ったって書いてあるのでそこがかわいい。
T:本当だね。ぴょんぴょこってどんな感じかな?みんな一回やってみようか。
CC:(みんなでぴょんぴょこ踊ってみる)
T:だれか代表で踊ってくれる人いる?
はやて:(ニコニコ顔で飛び跳ねて踊る)
たろう:(スキップしながら踊る)
T:みんな二人のたぬきさんみてどうだった?
ゆきこ:たのしそうなかんじがした。
ゆみこ:うれしそうにも見えた。
ここでは、たぬき役の子を見るという活動をしながら、自然とおかみさん目線で「たのしそうな感じ」「嬉しそうにも見えた」という発言が出てきています。最初はかわいいと言っていたところから、「楽しそう」「嬉しい」へとたぬきの行動の様子を少し詳しくとらえることができました。
このような読み聞かせをしながら、内容の大体を捉えていきました。子どもたちは「たぬきがかわいい」「おかみさんがやさしい」という感想をもったり、「なんでわなからにがしたの?」という疑問をもったりしています。そこで、一度全員が感じたことを表出するために、「たぬきの糸車のすてきなところやいいところはあった?」と問いかけました。その後のやりとりは以下の通りです。
T:たぬきの糸車ですてきだなって思ったところやいいなあって思ったところあった?近くの人と話してみて。
(あるグループの話し合い)
しんや:なんかさ、最初は悪いのにあとからよくなってた。
りおな:助けてもらったからお返しをしようと思ったんじゃない
しんや:つるの恩返しにめっちゃにてる。
りりな:たしかに。めっちゃにてる。
りおな:そこがすてきだなって思ったよ。
T:すてきなところ、いいなあって思ったところを教えてください。
たつみ:一番最初のたぬきは悪かったけど、それでも(おかみさんが)許してくれたから優しい。
ゆうし:(最後の場面)ここの跳びはねて帰ってるところ。
CC:いっしょ。おなじ。
T:ここ素敵だなって思った人?(半数くらいの手が上がる)
りゅう:だって、(挿絵のたぬきの)ほっぺたも赤いし嬉しそう。
みさと:すてきなところもあったけど、こわいところもあった。わなにつかまっているところはこわくない?
CC:そうそう、そこの感じ怖い。
CC:え~、でもさ、そこいいところだよ。
T:今、みさとさんは怖いっていったけど、しんたくんはいいところって思ったんだね。どうして?
しんた:わなにつかまったとき助けてあげたからここがいいと思う。
CC:そうそう、そこはいい場面だよ。
CC:えっ、こわいよ~。
同じ場面を取り上げても、子どもによって感じ方や考え方が違います。すてきなところやいいところを出し合っていく中で、そうした一人一人の読みの違いも表出してきました。この読みの違いは、今後子どもたちが問題解決をしていく一つのエネルギーになると思っています。
【学習活動③ 実習生に手紙を書くことを知り、一通目の手紙を書く】
実習生に手紙を書くという活動は子どもたちからは出てこないと考えたため、私の方から「実習生にみんながお勉強していることを伝えるために、たぬきの糸車のすてきなところやいいところをお手紙で伝えてみない?」と投げかけました。
すると、「やりたい。やりたい。」「めっちゃ書きたい。」「お返事返ってくるかな?」とみんな前向きに受け止めてくれました。
そこで、さっそくお手紙を書く活動に移ります。今回は、お手紙の用紙を6枚作成しました。それぞれお手紙に載せている挿絵が違います。子どもたちには、「自分が素敵だと思ったところの絵がついているお手紙を選んでね。」と伝えています。
このように挿絵が違う手紙を6枚用意したのは二つ理由があります。一つ目は、自分がどこに着目しているかを明確にするためです。一つの場面に着目して考えることで、自分がなぜここが素敵だと思ったのかにこだわる姿が見られるのではないかと思いました。二つ目は、文章を書くことが苦手な子にとっては、この手紙の用紙を選ぶという活動だけでも自分の考えをアウトプットする手段になりえると考えたからです。
実際子どもたちは、さっと手紙を選んで書いている子もいましたが、手紙の前でどれを取ろうか悩んだり、一度取っていった手紙を取り変えにきたりする子もいました。書くことが苦手な子も、自分が好きな場面の手紙を選んで「ここのたぬき(踊りながら帰っていくところ)が素敵だと思いました。」と書くことができました。その様子を見取り、「どうしてこの手紙にしたの?」と尋ねると、「だって、ぴょんぴょん踊りながら帰っていくところが楽しそうでいいと思ったから。」と話してくれました。
子どもたちが最初に書いた手紙をいくつか紹介します。
どの子も、自分がすてきだなと思ったところをよく書けています。読み聞かせの中で対話をしながら、内容を整理していったからこそ、一読しただけでも素敵なところを書けた子が多かったのではないでしょうか。静かに範読を聞く読み聞かせもいいですが、このように対話しながら読む読み聞かせも価値のあるものだと感じました。子どもたちがたのしみながらこの物語と出合ったことが分かります。
ただ、手紙の内容に目をむけると、まだ自分がすてきだと思った箇所を書いているだけにとどまっている手紙も多くあります。
これから単元を通して、この手紙の中に「たぬきやおかみさんの行動の理由」が表れてくることをねらっています。
さて、せっかく1通目を書きましたので、この手紙を実習生に送ってみることにしました。子どもたちは「やったー。」と大喜びです。
実習生からどんな手紙が帰って来るのか。そして、その手紙をきっかけにどんな学びの姿が見られるのか。
最後までお読みいただきありがとうございました。
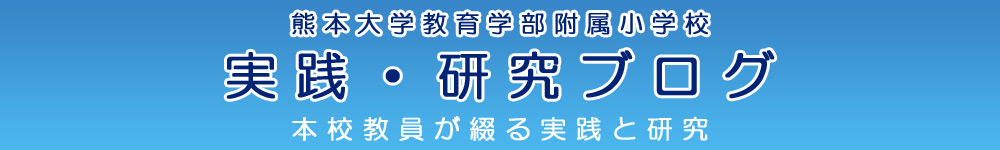





0 件のコメント :
コメントを投稿