たぬきの糸車④~チームの不思議を解決していこう~
公開日: 2025年10月14日火曜日
たぬきの糸車4時間目です。
前時では、場面の様子に着目してたぬきがいたずらしにくる理由を考え、実習生に改めて手紙を書きました。
実習生からきた返信はこちらです。
実習生からは、肯定的な手紙が返ってきました。子どもたちは、この手紙を聞いて大喜びです。中には、「こういう手紙が返ってきてほしくて頑張ったから嬉しい」ということを言っている子もいました。
この手紙が返ってきたことにより、「たぬきやおかみさんの行動の理由を書くといいこと」「不思議なことを解決して書くといいこと」が子どもたちの中に共有されていきました。
そこで、「まだみんなが不思議に思っていることある?」と尋ねると、以下のようなやりとりがありました。
【学習活動① 自分たちの不思議を出し合う。】
T:いたずらしたところ以外にも、みんなが不思議に思ったところってある?
ののか:たぬきが糸車の真似をして目を回している所が不思議です
CC:うん、同じ~
CC:そうそう目を回さなくていいもん。
T:真似をしなくてもいいのに、真似して目を回したのが不思議ってこと?
しんご:先生、あのさ、たぬきは糸車をもっともっと見たかったんだよ。
CC:あ~、めっちゃ見たくて見てたってこと?
CC:糸車が好きだったんじゃない?おもちゃみたいに。
このようなやりとりを通して、子どもたちが不思議に思ったことを出し合っていきました。一年生は、他の子が不思議をしゃべるとすぐに自分の考えを呟き始めます。そうしたつ呟きを拾いながら、なぜそこが不思議なのかを共有していきました。
【学習活動② グループで解決したい不思議を解決していく。】
ある程度、不思議が出終わったところでそれぞれのグループで解決したい不思議を決めて解決していく時間を取りました。
すると子どもたちの様相は以下のようなものに分かれていきました。
①劇だけをずっとやっているだけのグループ
このグループは自分たちの不思議を解決するというよりも劇を楽しみながらやっている様子でした。なので、不思議に向かうことはなく、グループ活動の時間が過ぎていきました。
②劇やインタビューをしながら話し合ってはいるものの、空想を話し合っているグループ
このグループでは話し合いは行われていましたが、叙述を根拠にしたものではなく空想の世界を広げているグループでした。例えば「どうしておかみさんはたぬきを逃がしたんですか?」「たぬきじるがおいしくなくて嫌いだから、たぬきをにがしました。」のような感じです。楽しそうに活動はしていましたが、不思議の解決には向かっていないようでした。
③インタビューをした後に本文に戻り考えているチーム
このグループは、本文シートを覗き込みながら、みんなで叙述に立ち止まりながら考えていました、叙述に線を引いたり、叙述と挿絵とをつなげたりしながら考えている姿もあり、自分たちの不思議について話し合っていました。
①、②、③の姿の中で最も多かったのは②の姿でした。12グループ中8グループがこの姿でした。残りの4グループは①の姿が2グループ、③の姿が2グループでした。
前時はグループ活動に移った際にも、グループ内で劇をしたりインタビューをしたりしながら活動ができていました。本時の姿でいうと③の姿が多かったです。
しかし、本時では②の姿が最も多く、前時とは違う様相になっていました。なぜこのような姿の違いが生まれたのかを考えました。
大きな要因の一つは、「何を考えたらいいかわからなかったこと」だと思います。前時はクラス全体で考えることが共有されていました。なので、グループに帰った際にも全体の課題になっていることを話し合えばよいということが明確でした。また、近くのグループの同じ内容を話しているので、グループを超えて交流した際にも同じ話題で話せています。しかし、本時は、それぞれのグループで考えることがバラバラだったので、グループを超えた際に違う話題が始まってしまいます。そこに、子どもたちは戸惑っている様子でした。
もう一つの要因は「場面の様子がはっきりしていなかったこと」です。前時では「山おくの一けんや」という場面の様子に着目した子どもの発言から、場面の様子を具体的に想像していきました。しかし、本時では全体で場面の様子を具体化する場面はなく、各グループに任せる形になりました。すると、考えの根拠となる叙述等を見つけることができず空想の世界で話していた子が多かったように思います。
以上の二点から前時と本時の話し合いの様相が異なっていたと考えられます。
もちろん、一年生の最後には個別の不思議であっても、自分たちで解決していく力を身につけてほしいと思っていますが、今の子どもたちの実態と照らし合わせたときに、個別の課題をそれぞれに解決していくことは子どもたちに無理をさせてしまうと判断しました。
【学習活動③ 実習生宛か担任宛の手紙を選んで手紙を書く】
本時では、様々な子どもたちの様相があったので、不思議を考えられた子もいれば考えられていない子もいます。そこで、本時では実習生に手紙を書くことを全員にさせるのは難しいと思いました。そこで、不思議が解決できて手紙が書けそうな子は実習生に手紙を、まだ不思議が解決していないときは私宛に手紙を書くようにしました。
子どもたちの振り返りを紹介します。
子どもたちは36人中22人の子が私宛の手紙を選び、不思議なことや解決していないことを書いていました。さらに実習生に手紙を書いた子も、「実習生へ なんでたぬきはおどりながらかえったのか、わかりません。」などのように疑問を書いている子もいました。子どもたちにとってこの一時間は、自分が分からないことに気付いた一時間だったのかもしれません。
最後までお読みいただきありがとうございました。
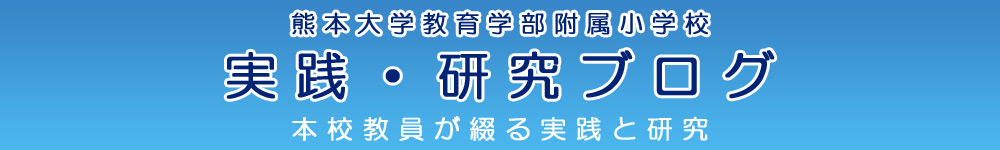
.jpg)
.jpg)


0 件のコメント :
コメントを投稿